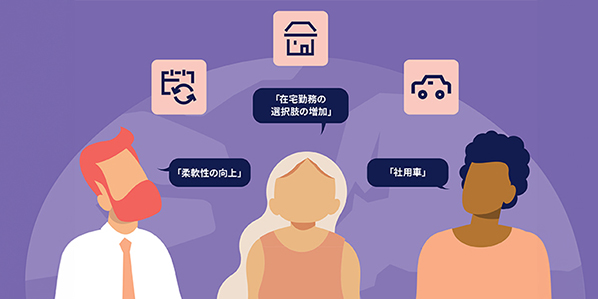社会保険の扶養手続きは、従業員のライフプランや家計に直接影響を与えるため、人事労務担当者には制度への正確な理解が不可欠です。従業員の収入状況や家族構成の変化によって、扶養の可否や、手続き内容が変動します。
本記事では、人事労務担当者の皆様に向けて、社会保険における扶養の基本的な考え方と具体的な認定基準や必要な手続きについて解説します。
正しい知識を身につけることで、従業員への適切な案内や、給与計算における正確な処理が可能になります。ぜひ最後までお読みいただき、日々の業務やご自身の判断にお役立てください。
※本記事に記載している法律や制度は、執筆時点での情報を基にしています。その後の改正や変更がある可能性があるため、最新の状況については、関連機関の公式サイトなどでご確認ください。
社会保険の扶養とは
社会保険における「扶養」とは、主に健康保険と厚生年金保険に定められた制度上の概念です。具体的には、一定の条件を満たす家族(被保険者の配偶者や子どもなど)が「被扶養者」として認められることで、保険料を支払うことなく健康保険の給付や年金の保障を受けられる仕組みです。
社会保険の扶養は、所得税法上の「扶養控除」とは異なる制度であり、それぞれ認定基準が異なります。よく混同されやすいため、「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養(扶養控除)」という2つの制度があることをしっかり押さえておきましょう。
なお、当記事で解説する「社会保険の扶養」とは健康保険と厚生年金保険に関するものであり、雇用保険や労災保険は含みません。
被保険者と被扶養者
社会保険の扶養制度を理解するために、「被保険者」と「被扶養者」の違いを整理します。
被保険者とは、会社などを通じて社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している従業員本人を指します。保険料は、原則として会社と被保険者本人が半分ずつ負担する仕組みです。
一方、被扶養者とは、被保険者によって主に生計を維持されている家族のことです。被扶養者になることで、被扶養者自身が健康保険料・厚生年金保険料を直接負担せずに、健康保険の給付などを受けられるようになります。
認定対象者
「認定対象者」とは、社会保険において被扶養者として認定される可能性のある家族の範囲です。原則として、被保険者と三親等以内の親族が対象であり、扶養に認定されるかどうかは被保険者との続柄や生計維持関係が問われます。また、続柄によっては同居要件を満たすことも必要です。
加えて、原則日本国内に住所があることも条件となります。ただし、留学など日本国内に生活の基盤があると認められるものは除きます。
扶養家族
「扶養家族」とは、法律で明確に定義された用語ではありませんが、一般的には、経済的な援助を受けて生活している家族全般を指します。
社会保険の文脈においては、多くの場合「被扶養者」とほぼ同義で使われます。ただし、所得税法上の扶養控除の対象となる「控除対象扶養親族」とは範囲や収入要件が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
社会保険の被扶養者の条件(範囲)
社会保険の被扶養者として認定されるためには、被保険者との関係や生計維持の実態、収入に関する一定の条件を満たす必要があります。まず、範囲としては以下の通りです。
- 被保険者の配偶者(内縁関係含む)、父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、兄弟姉妹
- 被保険者と同居している3親等内の親族(1.に該当する人を除く:配偶者の父母、祖父母など)
- 被保険者と同居している内縁関係の配偶者の父母および子ども(配偶者が死亡後の場合も含む)
1.に関しては、必ずしも被保険者と同居していなくても問題ありません。例えば、被保険者から仕送りを受けて生活している別居の父母なども、条件を満たせば被扶養者となり得ます。

【出展】全国健康保険協会 被扶養者とは?
生計維持の条件
被扶養者は、「主として被保険者の収入によって生計を維持されている」状態であることが必要です。
具体的には、「認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)」という条件です。これは、いわゆる「130万円の壁」と呼ばれるものです。加えて、同居の有無に応じて、以下に該当する方が対象となります。
- 同居の場合:認定対象者の年間収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満(ただし、認定対象者の収入が年間130万円未満であり、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合は、生計維持関係が認められることもあります。)
- 別居の場合:被保険者からの仕送りが認定対象者の年間収入以上
なお、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。
扶養の収入要件に含めるもの・除外するもの
被扶養者の「収入」の考え方は幅広く、パート・アルバイト等の給与収入のほか、雇用保険の失業等給付、必要経費を差し引いた自営業の事業所得、株式の配当金、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金、不動産収入、その他被保険者以外からの仕送り(養育費など)も含まれます。
例外として収入要件から除外されるのは、退職金(一時金)や不動産・株式の売却収入(譲渡所得)、保険金(一時金)、宝くじの当せん金、結婚祝い金など、継続性のない一時的な収入です。
また、収入の計算は、過去の実績ではなく、扶養認定時点での「今後1年間の収入見込み」で判断する点にも注意が必要です。年間130万円を超えない範囲で考えると、給与収入では月額108,333円以下、失業等給付では日額3,611円以下が目安となります。
なお、2024年10月の法改正により、従業員51人以上の企業で働くパート・アルバイトは、週20時間以上かつ月額賃金8.8万円(年換算約106万円)以上などの条件を満たすと、自身で社会保険に加入することが義務付けられました。いわゆる「106万円の壁」です。
この条件に該当すると社会保険の扶養には入れないため、被扶養者である場合は、扶養から外す手続きが必要です。
社会保険の扶養手続き
社会保険の被扶養者に関する手続きは、主に「新たに家族を扶養に入れるとき」と「扶養している家族に異動があったとき」に発生します。手続きは原則として、事業主(会社)を経由して、日本年金機構または加入している健康保険組合に対して行います。
それぞれの扶養手続きの流れを解説します。
従業員が家族を被扶養者にするとき
従業員が結婚や出産などにより、家族を新たに社会保険の被扶養者として加えたい場合、会社経由で以下の手続きが必要です。
提出書類
「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出が必要です。この届書には、被保険者(従業員)の情報と、新たに被扶養者となる家族の氏名、生年月日、続柄、収入状況、マイナンバーなどを記載します。
被扶養者が配偶者で、20歳以上60歳未満で国民年金第3号被保険者に該当する場合は、同じ様式で「国民年金第3号被保険者関係届」も提出できます。
添付書類
届出の内容に応じて、添付書類が異なります。
【必須書類】
- 続柄を確認するための書類(住民票、戸籍謄本など)
- 収入要件を確認するための書類(所得証明書、課税証明書、年金振込通知書のコピー、失業給付の受給資格者証のコピーなど)
【該当する場合のみ】
- 別居の場合:仕送りの事実と金額を確認できる書類(預金通帳のコピー、現金書留の控えなど)
- 内縁関係の場合:内縁関係を確認するための書類(両人の住民票、戸籍謄本など)
具体的な必要書類は、日本年金機構や各健康保険組合の公式サイトで確認するか、管轄の年金事務所・健康保険組合の担当者に問い合わせるとよいでしょう。
提出期限
原則として、扶養の事実が発生した日から5日以内に事業主へ提出を行います。提出が遅れると、扶養認定が遅れたり、場合によっては遡って認定されなかったりする可能性もあるため、速やかな手続きが重要です。
手続きの流れ
一般的には以下のような流れとなります。
- 従業員から家族を扶養に入れたい旨の申し出を受ける
- 事業主は必要な書類(被扶養者(異動)届など)を従業員に渡し、記入と必要に応じて添付書類の準備も依頼する
- 従業員が記入した届書を必要な添付書類とともに事業主へ提出する
- 事業主が提出された書類の内容を確認し、日本年金機構または健康保険組合に提出する
扶養から外す場合や被扶養者の届出事項の変更があったとき
被扶養者として認定されている家族が就職をして自ら社会保険に加入した場合や、収入要件を満たさなくなった場合、あるいは届出事項に変更が生じた場合には、再度「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出が必要となります。
ここでは、主なケースと手続き方法を解説します。
扶養から外す手続きが発生する主なケース
- 被扶養者が就職・転職し、自身で社会保険に加入したとき
- 被扶養者の収入が増加し、収入要件を満たさなくなったとき
- 被扶養者が死亡したとき
- 被扶養者である配偶者と離婚したとき
- 被扶養者が結婚等により他の被保険者に扶養されるようになったとき
- 被扶養者が独立して生計を別にしたとき
- 被扶養者が日本国外へ転居したとき(留学など一部例外あり)
- 同居が条件となる親族が別居することになったとき
- 被扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したとき
届出事項の変更が発生する主なケース
- 被扶養者の氏名が変更になったとき(結婚・離婚など)
- 被扶養者の戸籍上の性別に変更があったとき
異動手続きの方法
次の流れで異動手続きを行います。
- 提出書類:「健康保険 被扶養者(異動)届」
- 添付書類:内容に応じて、就職先の資格確認書または健康保険証のコピー、死亡診断書のコピー、住民票など
- 提出期限:異動の事実が発生した日から5日以内
扶養から外す手続きが遅れると、本来は受けられない保険給付を受けてしまい、後日医療費の返還を求められたり、保険料の調整が発生したりする可能性があります。そのため、速やかな手続きを行いましょう。
社会保険の扶養手続きに関する注意点
最後に、社会保険の扶養にまつわるよくある疑問や注意点をQ&A形式で解説します。手続きを忘れてしまった場合の影響や、失業手当受給時の扱い、年途中で収入状況が変わった場合の考え方など、見落としがちなポイントを確認しましょう。
被扶養者(異動)届を提出し忘れたらどうなりますか
扶養から外すべきケースで届出を忘れてしまうと、医療費の遡及支払いが生じるなど、トラブルにつながる可能性があります。
例えば、被扶養者の収入が増加したにもかかわらず扶養を外す手続きを行わず、従業員がそのまま健康保険証を使用し続けた場合、後から発覚すると資格喪失日までの遡りが行われることとなり、資格喪失日以降に健康保険で受けた医療費(通常7割)について、返還を求められます。
簡単に言えば「本来は健康保険が適用されない状態だったにもかかわらず、給付を受けてしまったので、その分を返してください」という請求が従業員のもとに届くことになります。
これは従業員にとって大きな経済的負担になりかねません。また、会社としても異動届の未届出が明るみに出ることで、担当者や企業の信用問題にも影響を与える可能性があります。
配偶者が退職をして失業保険を受給する場合、扶養に入れますか
配偶者が退職し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給する場合、その受給額によっては社会保険の扶養に入れないことがあります。
判断基準となるのは、基本手当の日額です。日額が3,612円(60歳未満の場合、130万円÷360日≒3,611.1円)以上の場合、その受給期間中は原則として収入要件を満たさないと判断され、被扶養者となることはできません。
そのため、ハローワークで基本手当の受給手続きを行い、受給資格者証が交付されたら、記載されている基本手当日額を必ず確認しましょう。日額が基準額未満であれば、他の要件を満たす限り扶養に入ることが可能です。
基準額以上の場合は、受給期間中は扶養に入れないため、配偶者自身で国民健康保険などに加入する必要があります。なお、受給が終了すると、再度扶養手続きを行うことができ、待機期間中(7日間)や給付制限期間中(1〜3ヶ月)は、まだ収入が発生していないため、他の要件を満たせば扶養に入ることが可能です。
年の途中から収入を得た場合、年収要件に影響はありますか
年収要件(年間収入130万円未満)の判断は、扶養認定を受ける時点(または収入が発生した時点)以降の「年間見込み収入」で行うのが原則です。過去の収入や、一定期間(1月から12月など)の収入ではなく、今後1年間の見込み収入が130万円未満かどうかで判断されます。
年の途中からパートなどで働き始めた場合、その時点から今後1年間の収入が130万円未満に収まるかどうかで判断します。具体的には、月収が継続的に108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える方の場合、働き始めた時点から収入要件を満たさないと判断され、扶養から外れる手続きが必要になる可能性が高いです。
例えば、月収11万円で働く契約をした場合、年間見込み収入は132万円となり、130万円を超えるため、働き始めた月から扶養を外す必要があります。
また、短期間だけ収入が増え、その後下がる見込みであれば、直ちに扶養から外さなくても良いケースもあります。厚生労働省では、一時的な収入増加に対し、事業主の証明を添付することで、収入基準を超えても扶養にとどまれる措置を認めています。
特例措置の利用を希望する従業員が発生した際は、一時的な収入増加かどうかを確認し、加入している健康保険組合等に確認したうえで、証明書の作成を検討しましょう。
【参考】厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
給与計算アウトソーシングを活用しよう
社会保険の扶養認定基準や手続きは複雑で、収入要件の判断、必要書類の確認、法改正への対応など、人事労務担当者には専門的な知識と細やかな注意が求められます。特に、被扶養者の収入状況は変動しやすく、定期的な確認や正確な対応も必要となります。
扶養関連業務を含む給与計算プロセス全体の負担を軽減し、正確性を高めるために、給与計算アウトソーシングの活用は有効な選択肢の一つです。
ADP Japanは、日本で2004年にサービスを提供開始してから20年以上がたち、製薬・金融・ITなど多様な業種のニーズに応え250社以上、従業員規模1〜6,000名の給与計算業務を支え続けてきました。
グローバルの顧客数は110万社以上、140か国超の実績数を誇り、米国企業売上高ランキングのFortune 500に30年連続で選出されています。45か国語を扱う多言語対応に強みを持ち、外資系企業やグローバル人材を雇用する企業の給与計算を得意とします。給与計算アウトソーシングをご検討中の方は、ぜひお問い合わせください。
まとめ
本記事では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)における扶養の基本的な仕組みや認定条件、具体的な手続きと疑問点について解説しました。
社会保険の扶養は、所得税の扶養とは異なり、独自の認定基準が存在しています。特に、収入要件の判定には、注意すべき点が多くあるため、医療費の返還など予期せぬトラブルにつながらないよう、速やかな届出が不可欠です。
近年では、「年収の壁」問題への対応や社会保険適用拡大など、制度を取り巻く環境も変化しています。人事労務担当者は、常に最新の情報を把握し、従業員へ正確な情報提供と適切な手続きを行うことが求められます。
扶養関連業務を含む給与計算は複雑で専門性が高く、担当者の負担も大きい業務です。自社での対応が難しい場合は、給与計算アウトソーシングの導入も検討してみてください。プロの力を借りることで、煩雑な扶養家族の手続きもスムーズに進み、結果として従業員が安心して働ける環境づくりにもつながります。
社会保険の扶養制度を正しく理解し活用することで、従業員と会社双方にメリットのある適切な労務管理を実現しましょう。